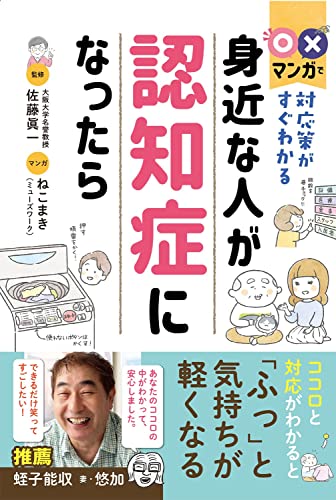認知症はある日突然になるのではなく、生活しているなかで「あれ?ちょっと変?」ということが増え、少しずつ症状が現れてきます。発症前やごく初期の段階で認知症とわかれば、進行をゆるやかにすることも可能です。認知症とは、認知症の発症リスクを低減する方法などについて、著者で認知症心理学専門家・大阪大学名誉教授の佐藤眞一さんに解説していただきました。
解説者のプロフィール
佐藤眞一(さとう・しんいち)
1956年東京生まれ。大阪大学名誉教授。大阪府社会福祉事業団特別顧問。博士(医学)。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学後、1999年に埼玉医科大学より博士号授与。明治学院大学心理学部教授、マックスプランク研究所上級客員研究員などを経て、2009年に大阪大学教授に就任し、2022年に定年退職。著書・共著は『認知症の人の心の中はどうなっているのか?』(光文社新書)、『認知症「不可解な行動」には理由がある』(SBクリエイティブ)、『マンガ 認知症』(ちくま新書)、『認知症plusコミュニケーション 怒らない・否定しない・共感する』(日本看護協会出版会)、『心理老年学と臨床死生学』(ミネルヴァ書房)など多数。
本稿は『〇×マンガで対応策がすぐわかる 身近な人が認知症になったら』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
イラスト/ねこまき(ミューズワーク)
最近のおじいちゃんはなんだかおかしい!
最近は友だちとの約束を忘れることが多いらしい…。

将棋が大好きだったのに最近はやりたがらないみたい…。

穏やかで優しいのに、突然、大声で怒りだすなんて…。

おじいちゃんどうしちゃったの?何かあった?歳のせい?

年齢も関係してますがそれって認知症の始まりかもしれません。
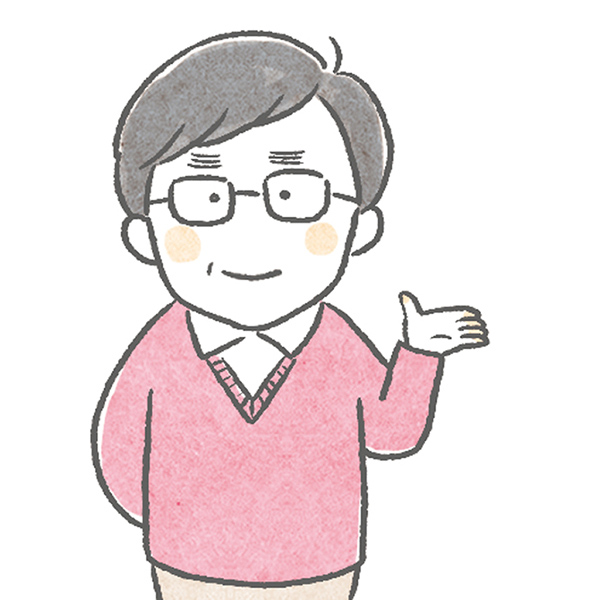
認知症って、そもそもどんな病気ですか?

3つの条件がそろったときに認知症と診断される
認知症は、次の3つの条件がそろった場合に診断されます。
(1)脳の疾患
脳が萎縮したり、血管のつまり・出血などの異変が起きる。
(2)認知機能が損なわれる
物忘れが増え、時間・場所・人物がわからなくなったり、今までできていたことができなくなったりする。
(3)生活機能が損なわれる
(1)や(2)の結果、料理や買い物、お金の管理などができなくなり、生活に差しさわりが出てくる。
つまり、日常生活に支障が出るようになって、はじめて「認知症」と診断されるわけです。
認知症は「病名」ではなく一連の「症状」を指す言葉で、認知症のタイプにはいくつかの種類があります。
認知症で現れる症状は人それぞれ。
同じ発言をくり返したり、物忘れやしまい忘れをすることは一般の人にもありますが、「5分前のことを覚えていない」など直近の記憶が残りづらいのが認知症の大きな特徴です。
「今朝の食事メニュー」や「さっき会った人の名前」が思いだせないのではなく、食事をしたことや人と会ったこと自体を覚えていないなど、記憶が丸ごと抜け落ちてしまうことがよくあります。

「なんか変だな」「いつもと違う」が発見のきっかけに
認知症の進行はゆっくりなため、「加齢のせいだろう」と考えがちです。
しかし、「なんか変だな」「いつもと少し違うな」と感じたら、早めに物忘れ外来や認知症外来を受診することをおすすめします。
専門外来に行きにくい場合は、かかりつけ医の受診でもOKです。
今のところ認知症の根本的な治療法は存在しませんが、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)と診断されても、認知症に移行しない人もいます。
そのような人には早期の治療に効果があります。

本稿は『〇×マンガで対応策がすぐわかる 身近な人が認知症になったら』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
軽度の認知障害なら認知症のリスクを防ぐことも可能です
運動・栄養など生活習慣の見直しは認知症に限らず人生において大切なことです。

リスク低減につながる生活
▼有酸素運動
1日30分以上のウォーキングを週3日から。
水泳や水中ウォーキング、ヨガなどもおすすめ。
▼バランスのよい栄養
魚、緑黄色野菜、きのこ・海藻・豆類、フルーツを積極的にとる。
高カロリー、高塩分は避ける。
▼禁煙
認知症のリスクを下げるだけでなく、健康上の利点が多い。
▼適度な飲酒
1日あたり、ビールは350ml缶1本、ワインはグラス1杯、日本酒は1合以内、焼酎は半合以内。
週1回は休肝日を設ける。
▼体重管理
65歳以下は体格指数(BMI)※を30以内に保つのがよい。
高齢者ではBMIに関係なく体重の増減が少ないほうが発症リスクを下げる。
※体格指数(BMI)= 体重kg ÷(身長m × 身長m)
▼社会活動
趣味の活動、ボランティア、地域活動、家族とのやりとりなど人との交流は脳を活性化させる。
▼健康管理
高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病、うつ病は認知症リスクを高める。
うつ病の場合、抗うつ薬で治療してもリスクは低減しない。
生活習慣を見直して認知症の発症リスクを低減
人は加齢とともに心身にさまざまな変化が現れます。
高齢になればひざや腰に痛みが出始めたり、「トイレが近い」「階段が苦痛」などの理由で外出がおっくうになることはよくあります。
若いころに比べるとどうしても気力が衰え、記憶力は20代をピークに下降線をたどるといわれます。
加齢による変化だけでもこんなに多くあるわけですが、認知症の人はそのうえに脳の病気が重なっていることになります。
認知症にはいくつかの種類がありますが、いずれもある日突然発症するわけではなく、軽度認知障害(MCI)の段階を経て徐々に進行します。
MCIの人のうち認知症に移行するのは約15~40%といわれ、記憶の低下が目立つアルツハイマー型認知症に移行する「健忘型MCI」の場合は、この間に有酸素運動を続けたり、人との会話や交流を保つことで認知症への進行を遅くできるとされます。
なお、脳血管性認知症の場合は、日々の散歩やウォーキング、バランスのよい食事、禁煙、過度の飲酒を避けるなど、生活習慣を見直すことで認知症になるリスクを低減する効果があるといわれています。
▼レビー小体型や前頭側頭型のように記憶の低下が目立たない認知症に移行するMCIは「非健忘型MCI」と呼ばれる。
本稿は『〇×マンガで対応策がすぐわかる 身近な人が認知症になったら』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
介護のコツこれも大事
認知症はある日突然になるのではなく、生活しているなかで「あれ?ちょっと変?」ということが増え、少しずつ症状が現れてきます。
発症前やごく初期の段階で認知症とわかれば、進行をゆるやかにすることも可能です。
本人の「なんか変」な気持ちは尊重する
初期のころは、家族よりも本人のほうが自分の変化に敏感です。
物忘れの性質も今までとは違うと気づき、「最近バカになっちゃった」と深刻になったり、「風邪気味だから寝る」などと部屋に引きこもることが多くなります。
本人の「なんか変」は軽く流さず、「認知症外来」や「物忘れ外来」など認知症の専門医の診断を受けましょう。
正確な診断が早いほど進行をゆるやかにしたり、これまでの生活をできるだけ維持する準備ができます。
また、脳腫瘍やうつ病などほかの病気からくる症状の場合もあります。

まずは本人の希望を聞いてみる
本人が不安を抱えていても、病院や検査を嫌がることがあります。
その場合は、今何に困っているのか、どうして欲しいのかを本人に聞いてみます。
たとえば「スーパーで何を買うのか忘れて困る」というのであれば、事前に家族がメモに書いておくなど、改善法を話し合っておくと不安を軽減できます。
とはいっても、やはり早めの診断が大切。嫌がるようなら、家族の受診についてきてと連れだし、本人も一緒に診てもらうなど、様子を見ながらかかりつけ医に相談を。
かかりつけ医がいない場合は、近くの地域包括支援センターでサポートを受けられます。

家族も認知症への理解を深めて
たとえば、理性を司る前頭葉に障害が起きると感情の抑制がむずかしくなり、突然怒りだしたり、暴言を吐くなど、周囲が驚く言動が見られます。
家族も感情的に怒ってしまいがちですが、それでは本人のプライドを傷つけたり、興奮をあおるだけ。
どうしてそうなってしまうのか、どうしたら落ち着くことができるのか、認知症の症状を理解し、本人の気持ちを想像することがお互いのためです。

◇◇◇◇◇
なお、本稿は書籍『〇×マンガで対応策がすぐわかる 身近な人が認知症になったら』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。認知症は特別なものではなく、どんな人でも歳をとればとるほど発症する可能性が高くなります。不安ばかりが先立ってしまいそうですが、認知症は怖い病気でも、恥ずかしい病気でもありません。認知症になっても日々を楽しく過ごしている人はいますし、自分の生活を大事にしつつ、さまざまな介護サービスを利用しながら認知症介護に前向きに取り組んでいる家族もいます。終わりの見えにくい認知症介護を少しでもラクな気持ちで取り組んでもらえるよう、そんな思いを込めたのが本書です。認知症の人と穏やかに過ごすには、周囲の人にも理解してもらい、「お互いさま」の精神をもち社会全体で見守ること。そして、介護者の都合ではなく、認知症の人の側に立ってこの世界を見ることがポイントです。本書は、対応策がすぐわかる〇×マンガや、認知症心理学専門家による介護がラクになる対処法や認知症の人への接し方など、さまざまな事例をもとに、わかりやすく解説しています。