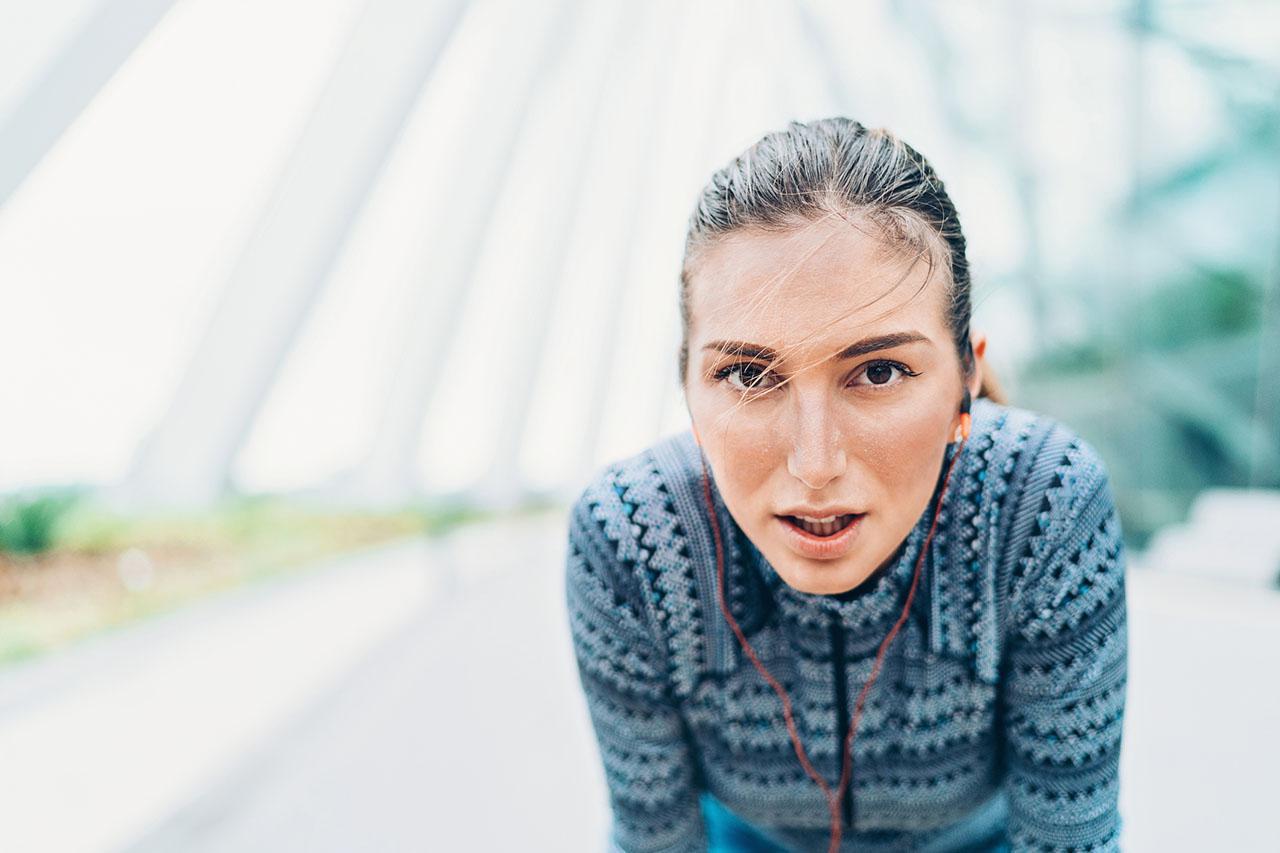こんにちは、家計コンサルタントの八ツ井慶子です。今回はコロナ不況を機に「家計防衛時代」がやってくるとして、その後に形成される新しい「社会経済」とはどのような社会(が望ましい)かをイメージしてみます。その上で、いまとはガラリ変わる家計の“新常識”もを考えてみたいと思います。「こんな考え方もあるのか」といった具合に、家計防衛時代の「心の準備」の一つとして、頭の片隅に置いておいていただけたらと思います。
執筆者のプロフィール

八ツ井慶子(やつい・けいこ)
生活マネー相談室代表。家計コンサルタント(FP技能士1級)。宅地建物取引士。(社)日本証券アナリスト協会検定会員。アロマテラピー検定1級合格者。城西大学経済学部非常勤講師。
埼玉県出身。法政大学経済学部経済学科卒業。個人相談を中心に、講演、執筆、取材などの活動を展開。これまで1,000世帯を超える相談実績をもち、「しあわせ家計」づくりのお手伝いをモットーに活動中。主な著書に、『レシート○×チェックでズボラなあなたのお金が貯まり出す』(プレジデント社)、『お金の不安に答える本 女子用』(日本経済新聞出版社)、『家計改善バイブル』(朝日新聞出版)などがある。テレビ「NHKスペシャル」「日曜討論」「あさイチ」「クローズアップ現代+」「新報道2001」「モーニングバード!」「ビートたけしのTVタックル」など出演多数。
▼生活マネー相談室(公式サイト)
▼しあわせ家計をつくるゾウ(Facebook)
「家計防衛時代」とは?
ここでいう「家計防衛時代」とは、簡単にいうと、大不況です。これから起こるとすれば、リーマンショックのレベルを大きく超えるでしょう。現在、金融政策によって支えられている株価が何かの拍子に崩れれば、実態経済は新型コロナウィルスの影響ですでに悪化していますから、規模もさることながら、これまでとは“形”が違う危機になると思われます。
これまでの危機では、最終的に政府や中央銀行による財政政策、金融政策によって「経済」を立て直してきました。が、現状すでに新型コロナ対策で両政策は目いっぱい発動しています。打つ手が限られる中で、規模の大きい危機となると、金融経済のリセット、まさにグレートリセットを意味するかもしれません。
“命がけの経済”が崩れようとしている
「いまの経済」は、新型コロナ対策と天秤に掛けられる「経済」です。いわば、“命がけの経済”。格差は世界の至るところにあり、悪化しています。今回のパンデミックでも露呈し、あらためて私たちに問題提起されました。その「経済」が、いま崩れようとしています。
「いまの経済」の最大かつ最悪の課題
新社会経済のキーワードは、スバリ「循環」だと思います。今の世の中に、私たちの暮らしに必要とされるモノは十分にあるでしょう。日本でいえば、「衣・食・住」のすべては余っています。被服ロス、食品ロス、空き家問題は、それぞれすでに社会問題化しています。
お金もモノも偏り過ぎている
世界に目を向けても、「食」でいうと、世界最大の人道支援機関である国連WFP(国際連合世界食糧計画)によれば「(世界の)すべての人が食べるのに十分な食料が生産されている」のだそうです。にもかかわらず、現実は「6憶9,000万人がいまだに毎晩空腹を抱えたまま眠りについて」います。残念ながら、日本でも餓死のニュースを時折目にすると、「“経済大国”って何だろう」といつも思うのです…。
一方で、世界の富豪上位2,153人が2019年に独占した資産は、最貧困層46憶人が持つ資産を上回るのだそうです(国際非政府組織オックスファム報告書)。
お金もモノもある。でも、“ある場所”が非常に偏っていて、本当に必要な人のところに「循環」していません。ここに「いまの経済」の最大かつ最悪の課題があると思います。

世界の富豪上位2,153人が独占した資産は、最貧困層46憶人が持つ資産を上回る。
“循環”する社会経済とは?
「お金」と「財・サービス」の交換(消費)がうまく“循環”するような社会経済を構築できれば、格差や貧困の問題はグッと改善方向に向かっていくのではないでしょうか。このとき重要なのは、「お金の量に上限を設けること」と、何らかの制度(税制や社会保険など)で富の再分配を行い、「少数の人に富が集中しないようにすること」です。
そして、私たちの意識も大きく変える必要があります。さまざまな事情をかかえて働けない人がいます。傷病、障がい、育児、介護、若年、高齢、被災等々。「働かざる者食うべからず」ではないのです。
また、世界的に長寿化は進んでおり、日本はその最先端をいっています。「人生100年」ともなれば、これまでのように、学業を終えてから定年まで、毎日のように働き続けられるでしょうか。ちなみに、私はイヤです。そもそも、「人生100年」でさえも怪しいものです。何歳まで人間の寿命が伸び得るかは、専門家でも意見が分かれるのだそうです。仮に120歳、150歳となっても、私たちが安心して暮らせる社会経済の構築を念頭に置く必要があるでしょう。
積極的な“失業者”の存在を認める社会
となると、健康な人であっても、「休む(休業)」時間をみずからの選択で持ちつつ、長く働くことが「新しい働き方」になっておかしくありません。そうなれば、世の中には、「働けない人」以外にも、ある一定程度の積極的な“失業者”が恒常的に存在することになります。
つまり、私たちすべての人が、長い人生の中で“失業”し得るわけです。超長寿社会でのポイントは、「安心して休める環境づくり」でしょう。そこでは、意識改革が重要になります。どのような事情にせよ、“働いていない人”も、「循環」の一翼を担う社会の一員だと認め、かつ「消費者」としても、その存在価値を広く認知するという意識改革です。

超長寿社会で大事になるのは、安心して休める環境づくり。
ベーシックインカムの可能性
このように、富の再分配は、“すべての人”を対象とすることが大切です。すべての人が生活できる基盤を作ることができれば、「循環」のベースができるのではないでしょうか。個人的には、「ベーシックインカム」がふさわしい制度ではないかと思っています。
※ベーシックインカムとは、政府が性別、年齢に関わらずすべての国民に、生活に必要な最低限の金額を無条件で支給する制度。貧困削減のほか、複雑化した社会保障を一本化して行政の事務コストを減らす効果や、少子化対策にも有効とされる。(出典:野村證券 証券用語解説より)
生活を軸とした社会経済へ
具体的な制度の議論は別としても、何らかの形で「生活の基盤」ができれば、私たちの人間としての尊厳は守られ、長い人生を「より人間らしい活動」に費やすことができます。精神疾患や自殺、さまざまな犯罪も減少するでしょう。ストレスレスな人が増えれば病気も減り、医療費の削減にも大きく貢献することでしょう。
「いまの経済」から脱却しない限り、このような「公平で平和な社会」は築けないのではないかと思います。いまの「金融システムを軸とした経済」を終わらせ、「私たちの生活を軸とした社会経済」を創造するタイミングとしては、新型コロナによる不況に直面している今は、とてもよい条件が揃っているように思うのです。
これからの家計の“新常識”は?
では、その上で、これからの家計の“新常識”を考察してみましょう。相も変わらず、私・八ツ井の独断と偏見によりますので、気軽に読み進めてみてください。
(1)新常識▼人生の3大資金の(事実上の)消滅
「人生の3大資金」とは、教育資金、住宅資金、老後資金を指します。長い人生の中で高額なお金がかかり、「事前の準備が大事」とされる資金です。パーソナルファイナンス(お金の管理)でどう準備をしたらいいか、ということが家計アドバイスにおいてのポイントにもなっています。実際、家計相談では、この3大資金の準備をキッカケに来られる方が多くいらっしゃいます。
しかし今後は、この3大資金は消滅するのではないかと思っています。
「教育資金」については、教育を受ける機会の公平化、少子化対策も相まって、現在進行中の「無償化」傾向が今後も進み、いまほどの負担はなくなるのではないでしょうか。
そもそも、「生活基盤が守られる社会」になれば、いまの高学歴志向も緩和され、「就職のための進学」ではなく、「学ぶための進学」の色合いを増し、いわゆるリカレント(循環教育=社会に出た後の学びなおし)も進むのではないかと思います。
「住宅資金」は、なくなるというより、その性質が大きく変わるでしょう。3大資金として住宅資金を語る時、基本的に「購入」を前提とし、頭金の準備、住宅ローンの組み方、返済の仕方などが家計管理上、重要とされています。
ですが、空き家が増えて、人口減少を迎えている現在の日本では、「家余り」が加速しています。供給が需要を上回れば、価値は下がります。全体的に住宅相場が下降すれば、持家ではなく、賃貸を選択する人も増えるでしょう。となると、「住宅資金」は「事前準備の費目」ではなく、家賃として、毎月の「支出の一費目」となる人が増えていくと思います。
そして、「老後資金」ですが、そもそも、なぜ老後資金を現役時代に準備しなければならないかといえば、「リタイア」を想定しているからです。高齢期に「リタイア=長く働かない期間」を持つためには、年金では足らない分を事前に準備しなくてはならない、という考え方です。
しかし、人生100年時代に備えて「そのぶん、より多くの老後資金を貯めましょう」というのはあまりに拙速な考え方だと思います。前述の通り、人間の寿命は伸び続けており、100歳が平均寿命の“ゴール”とも限りません。だとしたら、貯めることを促す策ではなく、寿命が伸びても安心して生活できる社会を作るための策が必要です。一定の生活の基盤が守られることを前提に、休みながらも長く働くことができる環境づくりは、一つの解決策ではないでしょうか。
「誰かの支出」は「誰かの収入」です。多くの人が支え合う(お金とモノが)循環する社会で、多くの人が「長く働くこと」を選択すれば、「老後資金を貯めること」は常識ではなくなっていくことでしょう。

休みながらも長く働くことを選択すれば、老後資金を貯めることは常識ではなくなっていく。
(2)新常識▼長期的なライフプラン作成の意義低下
「ライフプランを立てましょう」とは、これまたパーソナルファイナンス(お金の管理)では常識的に語られる言葉です。これはまさに、「3大資金の存在」が大きく影響しています。大きな資金が必要になれば、事前準備が必要です。これからの自分の人生でかかるであろう支出を事前に試算し、いつまでに、どのように準備していけば経済的に乗り切れるかを予測していくのに、ライフプラン表の作成は役立つからです。
家計管理の難しい点は、将来にかかる支出を予測して、準備する点です。ですが、人生の3大資金準備が事実上なくなれば、一気に楽になります。それでも、旅行や家電の買い替えなど、まとまった資金の短期的な支出は把握しておくとよいと思います。しかし、これまでのような「長期的なライフプランを作成する必要性」はグッと軽減されるでしょう。
(3)新常識▼リタイアの年齢は自分で決める
“働かない人”も「消費者」として生活できる状況が整うとしたら、「リタイアの時期は、自分で決める」という時代になるのではないかと思います。
そもそも、超長寿社会では、「休みながらも長く働くことを選択する人」が増えると思います。現在のように、一定の年齢で一律に「定年」とするのはそぐわなくなるでしょう。同じ年齢であっても、本人のスキルややる気、健康状態は個々で異なり、高齢者になるほど差が出やすいものです。加えて、デジタル化の進展で働き方が多様化する中、リタイアの年齢が一律というのは、ふさわしくなくなるでしょう。
(4)新常識▼お金の「使い方」がより大事に
これからは、「お金を貯めよう」ということも、「家計の常識」ではなくなってくると思います。個人的に、「貯め方よりも、使い方が大事です」と、もう何年も指摘し続けているのですが、一般的には、まだまだ認知されていません。
3大資金の必要性が消滅する中で、「どうお金を貯めるか」の重要度は小さくなります。「貯める」のも「使う」のも、その源泉は「収入」ですから、コインの裏表の関係です。貯めようと思ったら「使い方を正すこと」になるので、今後は、より多くの方の意識が「使い方」に向けられると思います。
また、このことは、キャッシュレス化が進展する中の「金銭教育」としても非常に大きな意義を持ちます。キャッシュレス決済では、「ムダづかいが増えやすい」とはよく指摘されることです。特に、若いデジタルネイティブ世代は、キャッシュレス時代で育っていくため、ムダづかいを抑えるのに「いったん現金に戻りましょう」が通じません。お金の“形”がどうであっても、周りに流されることなく、「自分軸で買い物をするスキル」は、より重要になっていくでしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。これからの家計の新常識を4つ、挙げてみました。
「過去の常識」が「現代の非常識」であることは、歴史上もたくさんあります。家計の常識も同様です。老後資金を貯める“常識”も、平均寿命の伸びが影響していました。今後さらに寿命が伸びれば、その常識=貯める“常識”が、さらに変わってもおかしくありません。数年で変わるのか、数十年かかるのか分かりませんが、私たちの暮らしに大変革が起こることは、ほぼ間違いないであろうと思っています。
これらのことを「頭の体操」と思って、みなさんもどのような社会経済を構築したいか、そのとき自分はどういった暮らしをしたいのか、考えてみてはいかがでしょうか。それにふさわしい考え方がこれからの“新常識”として語られることになると思います。
文/八ツ井慶子(家計コンサルタント)