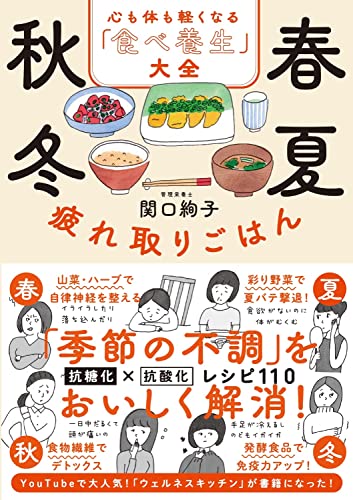ドレッシングにしても、タレやソースにしても、試しきれないくらいいろいろな市販品があります。でも、本当に自分の好みにぴったり合うものに出会うのは難しい……。そんな悩みを解消してくれるのが、手作り調味料。塩分を減らしたり、酸みを加えたりということも自在です。そして何より安心です。手作り調味料について、書籍『春夏秋冬 疲れ取りごはん 心も体も軽くなる「食べ養生」大全』著者の関口絢子さんに解説していただきました。
解説者のプロフィール
関口絢子(せきぐち・あやこ)
料理研究家・管理栄養士。東京都生まれ、川村学園短期大学食物学科卒業。「食とアンチエイジング」の関係が注目されていなかった15年以上前から、インナービューティースペシャリストとして情報を発信し、先頭を走り続ける。テレビや雑誌等のメディアを中心に、健康・美容・ダイエットに関するレシピや栄養情報を提供。2020年に開設したYouTube「関口絢子のウェルネスキッチン」は登録者15万人を超える人気チャンネルとなっている。米国栄養カウンセラー、ヘルスケアプランナー、日本抗加齢医学会認定抗加齢指導士。
本稿は『春夏秋冬 疲れ取りごはん 心も体も軽くなる「食べ養生」大全』(KADOKAWA)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
イラスト/祖父江ヒロコ
毎日の食事に健康と自分好みのおいしさをプラス
毎日の食事作りにたくさんの時間を使ったり、献立に悩んだりするのは大変です。
体にいいものを食べて疲れを寄せ付けない体になりたいですし、ワンパターンな料理が続いたり、栄養のバランスが心配だったりするのは心地よくありません。
この記事では、料理にプラスすることで、よりおいしくなったり、バラエティが豊かになったりする頼もしい脇役が主役です。
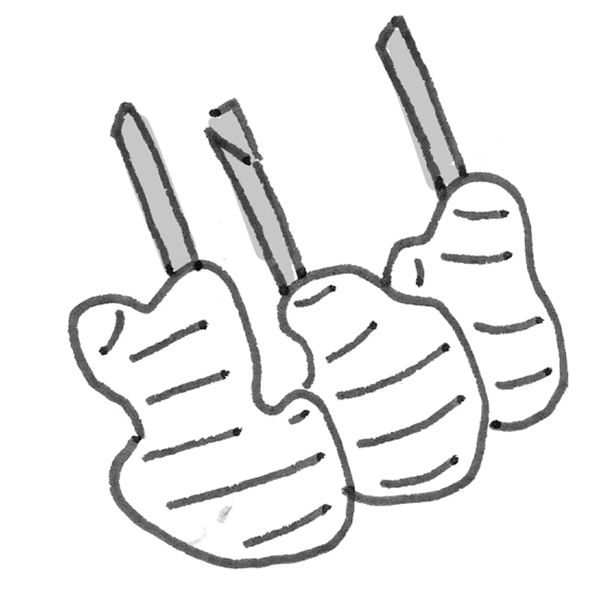
タレやソース、ジャムなど、料理に添えたり、味付けに使ったり。だからこそ、食べるときの印象を最後に決めるものといえそうなものたちです。
この決め手が本当に自分好みの味だったら? 不足しがちな栄養を、ちょっと補ってくれるものだったら? 手作りをすることで、それが実現します。
しかも、想像よりもずっと手軽。たくさん出回る旬の素材で「何を作ろうかな」と考えるのも楽しいですし、自分好みの味を探していろいろ調節してみるのもワクワクします。
ドレッシングにしても、タレやソースにしても、試しきれないくらいいろいろな市販品があります。でも、本当に自分の好みにぴったり合うものに出会うのは難しい……。そんな悩みを解消してくれるのが、手作り調味料。塩分を減らしたり、酸みを加えたりということも自在です。そして何より安心です。
その日の素材に好みの方法で火を通して(または生でも)、作り置きの健康調味料で味付け。それでおいしくて安心なら、毎日がとても快適です。そのために、身近にあるもので簡単に作れる調味料のレシピを紹介します。
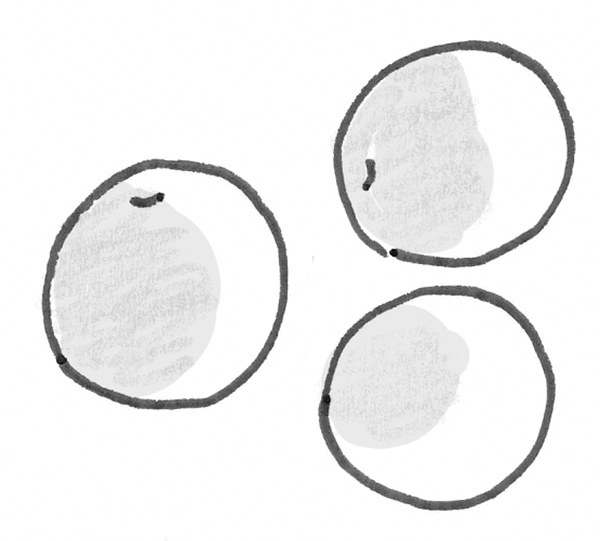
タレ、ソース、ジャムを作り置きする際の注意
▼保存容器は、密閉がしっかりできるガラス瓶を使う。
▼清潔な保存容器を使うこと。煮沸や消毒用アルコールなどで殺菌してから使う。
▼取り分け用の箸やスプーンを使う。食品を手で触らないこと。
▼水滴が出ないよう、食品は粗熱が取れてから保存容器に入れる。
▼冷蔵庫や冷凍庫で保存する。
▼薄味にするほど保存性が低くなるので、塩分や糖分が少ないものは早めに食べきる。
赤シソのポリフェノール×酢のクエン酸で健康増進
6月頃の限られた時期にしか出回らない赤シソには、βカロテン、ビタミンB群、ビタミンC、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、カリウムなど、ビタミンとミネラルがたくさん含まれています。
そして、赤シソ特有の紫色のもとになっているアントシアニン、香り成分であるペリルアルデヒドやロスマリン酸などのポリフェノールも豊富です。
ロスマリン酸はローズマリーやレモンバームなど、シソ科ハーブ類に多く含まれます
抗酸化力や抗炎症作用が非常に高く、アレルギーや花粉症の抑制、血糖コントロールのほか、近年では脳の機能や健康を維持するためにも役立つことがわかり、うつや不安の軽減にも効果があると報告されています。
アントシアニンは視力の向上や眼精疲労をやわらげ、ペリルアルデヒドが強い抗菌効果を発揮します。
血糖値の上昇を抑制し、肝臓の解毒を促進するなど、生活習慣病の予防にすばらしい効能があるシソに酢のクエン酸をプラスして、抗酸化、抗糖化、抗炎症などの作用をさらにアップさせた赤シソ酢。毎日大さじ1杯を目安にどうぞ。
酢の選び方
食酢には、穀類や果物を発酵醸造させて作る醸造酢と、酢酸(または氷酢酸)を薄めた液に砂糖や調味料、塩などを混ぜた合成酢があります。
合成酢は発酵させて作っていないので、健康効果が期待できるのは醸造酢。醸造酢には、米酢や黒酢などの穀類酢と果実酢があります。

酢の種類
米が原料の米酢、玄米が原料の黒酢のほか、小麦やトウモロコシから作られる穀物酢、ブドウを原料とするワインビネガーとバルサミコ酢、果物から作られるリンゴ酢などがあります。
黒酢やバルサミコ酢は熟成させるので深みのある味わいが特徴です。
スプーン1杯で慢性疲労を抑制赤シソ酢
▼疲労回復
▼ダイエット
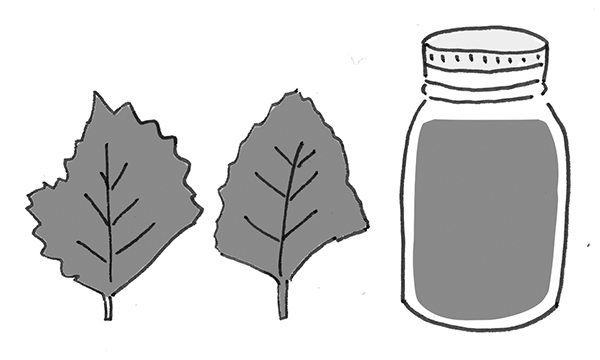
いろいろな料理に活用できる万能酢。シソの味はあまりしないので、普通のお酢と同じ使い方ができます。
甘酢にして、大根など白い野菜を漬けると、きれいなピンク色の甘酢漬けに。寿司酢として使うと、ほんのりピンク色の酢飯になります。はちみつや砂糖を加えて甘めにして、炭酸水で割るとビネガードリンクになります。
まろやかな味わいのリンゴ酢や黒酢でアレンジしても。
▼冷蔵保存 6か月
▼材料(作りやすい分量)
赤シソ…150g
酢…500ml
熱湯…500ml
▼作り方
(1)洗った赤シソを熱湯に入れ5分ほど熱を通す。
(2)湯に紫色が移りシソが緑色になったら、ザルにあげて水けを絞る。
(3)紫色になった湯と絞った水分を鍋に入れ、中火で煮詰める。
(4)水分が100mlくらいになったら火を止めて酢を入れ、保存容器に移す。
残った赤シソでもう一品シソの甘辛煮
▼疲労回復
▼材料(作りやすい分量)
赤シソ(千切り)150g、ショウガ(千切り)1片、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ2、テンサイ糖大さじ1、ゴマ油適宜、七味トウガラシ(お好みで)
▼作り方
赤シソとショウガをゴマ油で炒め、調味料で味をととのえる。お好みで七味トウガラシを入れる。おにぎりの具にするなど、ごはんのおともに。冷蔵庫で2週間保存可能。
酢を効果的に活用して内臓脂肪を解消
酢は穀物や果物をアルコールで発酵させ、さらに酢酸菌で発酵させた発酵調味料。原料や製法によって含まれる栄養成分は変わりますが、共通するのが酢酸です。
酢酸は食後血糖値の上昇抑制、糖化防止などに役立ちます。
また、糖や脂肪酸が脂肪細胞に取り込まれるのを防ぐので、脂肪を燃焼させながら蓄積を抑えます。
脂肪とひとことでいっても、体脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があります。
皮下脂肪は寒さから体を守ったり、クッションになったりします。
しかし、内臓脂肪はいろいろな悪さをする、体から追い出したいもののひとつ。
たとえば血管に負担をかける、コレステロールの増加、血圧や血糖値の上昇などの原因となります。
その結果、動脈硬化や糖尿病を引き起こしたりして、生活習慣病の原因にもなるやっかいなものなのです。
また、内臓脂肪がたまると、やせにくく太りやすくなるという悪循環を引き起こします。そんな弊害いっぱいの内臓脂肪を減らすのに、酢が役立ちます。
内臓脂肪
体に付く体脂肪には、皮下脂肪と内臓脂肪の2種類があります。この内臓脂肪は、生活習慣病に関わる危険な脂肪なので注意が必要です。
内臓脂肪が増えすぎると悪いホルモンを生み出し、生理機能に問題を及ぼします。
内臓脂肪の減らし方
内臓脂肪が付く原因は食べすぎやアルコールの飲みすぎ。そのため、食事制限をすれば内臓脂肪から減っていきます。
また、毎日大さじ1杯ずつ酢を取る生活を3か月続けると、内臓脂肪が減るといわれています。ドリンクにしたり、ドレッシングにしたり、工夫して続けてください。
食事といっしょに取ることでメリットがグンと大きくだし酢
▼腸活
▼疲労回復
▼ダイエット

体脂肪や内臓脂肪を減らすほか、血圧降下や疲労回復などの作用もあり、結果的に高脂血症や高血圧の予防にもなる酢。でも、酢をそのままかけるだけでは、味の変化が乏しくなりがちです。また、酢の味は刺激が強いので、薄めたほうがいいことも。
そこで、いろいろな料理に使えて味わいもプラスする、便利なだし酢をおすすめします。酢とだしの旨みで料理の塩分を抑えられるメリットもあります。
▼冷蔵保存 2か月
▼材料(作りやすい分量)
酢…300ml
干しシイタケ…2枚
昆布…12cm
煮干し(またはだしパック、カツオ節など)…5尾
▼作り方
(1)昆布は適当な大きさに切り、煮干しは頭とワタを取り2つに割る。
(2)保存容器にすべての材料を入れ、酢を入れる。※干しシイタケは水で戻さずそのまま入れる。
だし酢を使った簡単副菜切り干し大根のだし酢漬け
▼腸活
▼疲労回復
▼材料(作りやすい分量)
切り干し大根(戻したもの)100g、だし酢100ml、トウガラシ(お好みで)
▼作り方
切り干し大根をだし酢に15分ほど漬ける。お好みでトウガラシを混ぜても。冷蔵庫で1か月保存可能。※切り干し大根は乾物のまま使ってもOK。
◇◇◇◇◇
なお、本稿は書籍『春夏秋冬 疲れ取りごはん 心も体も軽くなる「食べ養生」大全』(KADOKAWA)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。やる気が出ない、重だるいなどの疲れに悩んでいませんか? 特に、季節の変わり目は、心や体に不調が起こりやすい時期です。「疲れ」や「なんとなく不調」を解決するのが、季節の食材や料理です。本書は、登録者数15万人を超える、著者のYouTubeチャンネル「ウェルネスキッチン」で人気があったレシピを選りすぐり、110品掲載しています。疲れの改善に特に大切な抗酸化・抗糖化を中心に、アンチエイジング、免疫力アップ、デトックスなど気になる情報を1冊に凝縮した集大成となっています。