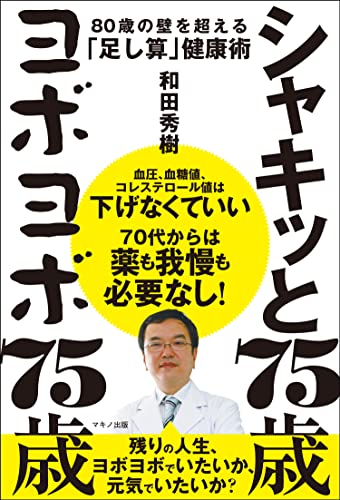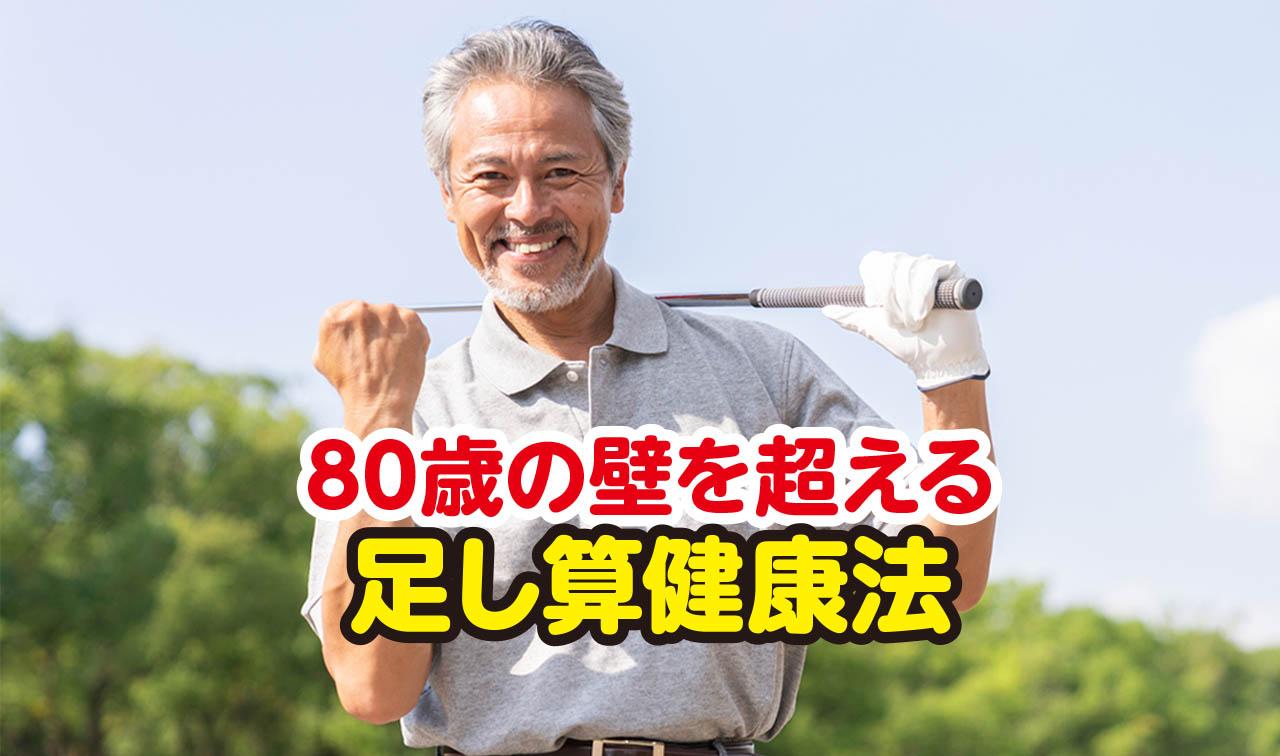老化による脳や体の衰えを避けることはできません。80歳以降、認知症やがんの有病率、要介護認定比率が急上昇し本格的に老化が進行します。しかし、悲観的になる必要はありません。「足し算」健康術をすることで、衰えをゆるやかにし80代の生活を変えることは可能です。「話題の医師が提案!幸せな日々のために…」をテーマに「徹子の部屋」(2022年9月7日)に出演し話題となった精神科医・和田秀樹さんに解説していただきました。
解説者のプロフィール
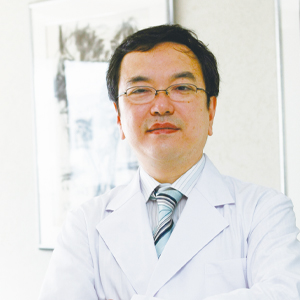
和田秀樹(わだ・ひでき)
1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。高齢者専門の精神科医として、35年近くにわたって高齢者医療の現場に携わっている。主な著書に『80歳の壁』(幻冬舎新書)、『70歳が老化の分かれ道』(詩想社新書)、『六十代と七十代 心と体の整え方』(バジリコ)、『老いの品格』(PHP新書)などがある。2022年9月7日「徹子の部屋」に出演。
本稿は『シャキッと75歳 ヨボヨボ75歳(80歳の壁を超える「足し算」健康術)』(マキノ出版)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
高齢者の活力を低下させる「引き算医療」
年をとるのは不安ですか?楽しみですか?
私が高齢者専門の精神科医として、患者さんの診療をスタートしたのは三十数年前のことです。
それほど昔のことではないと思うのですが、当時と今とでは高齢者の様子がまったく違います。
当時の60代、70代は外見や歩く姿もすっかり老け込んで、「おじいちゃん然」「おばあちゃん然」とした人が圧倒的多数でした。
還暦の祝いで、赤いチャンチャンコを着てもまったく違和感がなく完璧に似合っていました。
それがどうでしょう。
現在、私が診療や介護、講演会などでお目にかかる60代、70代で、いかにも老人、老人した人は滅多に見かけません。
三十数年前の同世代にくらべ、格段に若々しく元気です。60歳の人に赤いチャンチャンコを贈ろうものなら、「もっとオシャレなものが欲しいんですけど……」と言われることでしょう。
何歳まで生きるかという平均寿命も、着実に延びています。
1970年の平均寿命は、男性が69.31歳、女性が74.66歳。定年後に残された人生は、平均すると10年ちょっとでした。
いまや男性が81歳、女性が87歳を超えています(2019年)。
半数以上の人が90代まで生きる時代が、すぐそばまで来ています。
老後が10年も20年も長くなっているのです。
ここまで読まれて、「年をとるのは不安ですか?」、それとも「楽しみですか?」とたずねたら、おそらく半分以上の方は、寝たきりや認知症になってヨボヨボした自分を想像し、「不安」と答えるのではないでしょうか。
たしかに老化による脳や体の衰えを避けることはできません。
80歳以降、認知症やがんの有病率、要介護認定比率が急上昇し本格的に老化が進行します。
しかし、悲観的になる必要はありません。
「足し算」健康術をすることで、衰えをゆるやかにし80代の生活を変えることは可能です。
70代について、老年医学の権威として知られる米国の故・ベルニース・ニューガートン教授の興味深い学説があります。
ニューガートン教授は、介護や特別な医療が必要な高齢者と、必要のない元気な高齢者がいることに注目しました。
ニューガートン教授は、体力・知力がさほど落ちておらず、元気な高齢者が多い75歳までの層を「ヤング・オールド」、75歳を過ぎ、要介護になる人数が上昇傾向を見せる世代を「オールド・オールド」と呼びました。
ニューガートン教授の見解は実に納得のいくものです。
日本では75歳からは後期高齢者と呼ばれ、やはりこの年齢を境に脳卒中や心筋梗塞、がんなどさまざまな病気にかかるリスクが大きく増し、認知機能や運動機能の低下がみられるようになります。
けれども75歳までは、老いの兆しはあるものの、知力も体力も余裕があります。
元気なうちから体をよく動かし、栄養をしっかりとって、頭を使うように意識することが老化の速度をゆるめることにつながります。
70代は老いと闘える最後の世代です。「もう年だから」とあきらめることはありません。
元気に老後を送るには、70代以降は医療とのかかわり方も見直す必要があります。
たとえば、血圧が高いからと薬で血圧を下げると血液の循環が悪くなり、頭がぼんやりしてボケたようになったり、足元がおぼつかなくなったりするなど、かえって健康を損ねてしまいます。
このように数値が高いからと無理に薬で下げ、高齢者の活力を低下させる医療を、私は「引き算医療」と呼んでいます。
シャキッと元気に暮らしてこそ、よい晩年といえます。
引き算医療でヨボヨボになって過ごすなんて嫌だと思いませんか。
70歳以降は引き算ではなく「足し算」で心と体を調えていきましょう。
栄養や運動、性ホルモン、サプリメントなど、体に必要なものを足し算する「足し算」健康術をご紹介します。
いろいろなものを足し算すれば、75歳という節目を楽々乗りきり、シャキッと元気に80歳を迎えることができます。
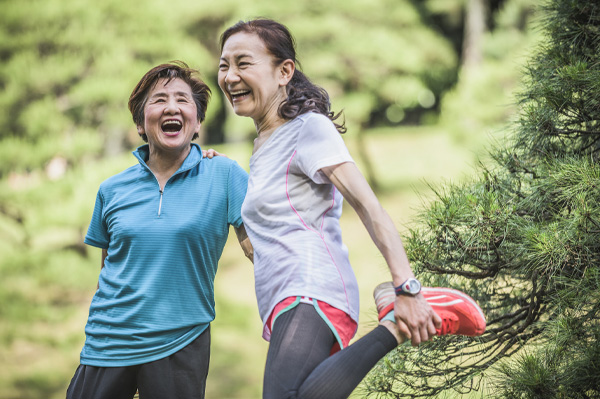
足し算健康法のすすめ
肉を食べる高齢者は元気で長生きする
老年医学の専門家である柴田博さんは、国内外の百寿者を対象に長期にわたる調査を行い、長寿の人に共通する健康習慣を分析しています。
『長寿の嘘』(ブックマン社)に研究成果がまとめられています。
豊富な臨床経験と綿密な調査に基づいた柴田さんの意見や指摘は説得力があり、高齢者の健康を考えるうえで私は大いに参考にしています。
柴田さんの指摘によれば、日本の長寿者の特徴は動物性たんぱく質の摂取割合が高いということです。
総たんぱく質(植物性+動物性)に占める動物性たんぱく質の割合は、1972年の国民栄養調査で示されている日本人の平均を大きく上回っていました。
当時の日本人の平均は48.7%と50%に達していませんでした。
一方、百寿者は男性59.6%、女性57.6%と欧米人並みの高さでした。
肉に含まれる動物性たんぱく質をとることで血液中に増えるアルブミンは、脳卒中、心筋梗塞、感染症の予防に効果があり、血液中のアルブミンが低い人ほど早期に死亡し、肉の摂取量が高くなるほど病気のリスクが低くなると柴田さんは指摘しています。
プロスキーヤーの三浦雄一郎さんは、80歳のときに3度目のエベレスト登頂に成功し、日本中をアッと驚かせました。
三浦さんの強靱な肉体と精神を支えているのは肉です。
週に何度か500gのステーキを平らげているそうです。
エベレストには登らないにしても、長い老後を若々しく過ごすために、日本人はもっと肉を食べたほうがいいと思います。

高齢になるほどコレステロールは必要
日本人の食生活は急速に欧米化したといわれていますが、肉の摂取量はアメリカ人の一日300gにたいし、日本人は100g程度です。
肉を敬遠する人は、「コレステロールが多いから食べない」と言います。
たしかに肉はコレステロールが多いし、コレステロールは動脈硬化の原因になります。
しかし、高齢者にはコレステロールが必要です。
日本の中でも長寿者が多い東京都小金井市の70歳の住民の血中コレステロール値と10年間の総死亡率を調べた調査では、コレステロール値が正常値よりやや高めのほうが死亡率が低いという結果が出ました。
コレステロールを恐れることはないのです。
コレステロールは意欲とかかわる男性ホルモンや女性ホルモンの原料になったり、脳にセロトニンを運んだりする働きがあります。
活動意欲を保つためにも、年をとったら日々の食事で肉を積極的に食べ、コレステロールをとる必要があります。

本稿は『シャキッと75歳 ヨボヨボ75歳(80歳の壁を超える「足し算」健康術)』(マキノ出版)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
62歳の私が実践する「足し算」健康術
ウォーキングとスクワットで血糖値をコントロール
私自身の健康管理についてもお話ししましょう。
私はいま62歳ですが、いくつも持病を抱え、まさに病気のデパートのような人間です。
2018年の正月、のどが異常に渇き10分おきぐらいに水を飲まないといられなくなり、夜中に何度もトイレに立つようになりました。
こんな状態が1カ月も続いたので、勤務先の病院で血糖値を測ったところ、なんと600㎎/㎗を超えていたのです。重症レベルの糖尿病です。
私はどうしてもインスリン注射を打ちたくなかったので、知り合いの医師に頼んで都内でインスリンを使わない治療をしている別の医師を紹介してもらいました。
いくつも薬を試しましたが血糖値はなかなか下がりません。
そこで私が始めたのが歩くことです。
運動をすると、筋肉でブドウ糖や脂肪の消費量が増え、とくに食後の血糖値の上昇が改善されます。
また、運動を習慣にすることで、血糖値を下げるインスリンの効きがよくなり血糖値の上昇を防ぎます。
当時の私は、移動に車かタクシーを使い、まったく歩かないという生活をしていました。
血糖値を下げるには下半身の筋肉をつけるのが効果的と知ったので、一日30~60分は歩くように心がけ、スクワットも日課にしました。
すると、早朝血糖値は200㎎/㎗程度、ヘモグロビンA1c(過去1~2カ月の血糖値を示す指標)の値は8前後まで下がりました。
健康診断でこの数値が出たら「高いですね。下げましょう」と言われるところです。
しかし、これ以上下げると頭がぼんやりする感覚があるので、私はこの数値でコントロールしています。
最近は300㎎/㎗くらいになりましたが、あまり症状がないので、よしとしています。
正常値より高めですが、のども渇かず夜中にトイレで目覚めることも一回くらいで済んでいます。

血圧は高めにコントロール
かれこれ10年来、血圧も高いときは220mmHgくらいありました。
頭痛などの症状がなかったので放っておいたのですが、知り合いの医師のクリニックで心臓ドックを受けると、いちじるしく心筋が肥大していることがわかりました。
血圧が高い状態が続くと、心臓に負担がかかり筋肉が分厚くなる心肥大が起こるのです。
心肥大が生じると心臓の血液を送るポンプの働きが低下するので、少し歩いただけで息苦しくなります。
心肥大の進行を防ぐためにいろいろ血圧の治療薬を試したところ、私の場合は、血圧を170mmHgより下げると体がだるくなり、頭もフラフラして仕事になりませんでした。
そこで170mmHgくらいでコントロールしていたら、ついに心不全の症状が出て、喘鳴もするし、息も切れるようになりました。
結果的に利尿剤を飲んだら症状は出なくなりました。
その後は少しくらい高めの数値でも、息も切れず生活に支障はないので、利尿剤を飲んで血圧は170mmHgくらいにコントロールしています。
心臓ドックで検査を受けていますが、心肥大は改善しています。
夕食では「ワイン」を楽しむ
一日の食事でいちばん大切にしているのは仕事を終えた後の夕食です。
午後8時か、遅いときは10時を回る日もざらです。夜遅くに重たい料理は食べないほうがいいといわれていますが、私はガッツリ派です。
赤ワインを飲むときは肉を、白ワインのときは魚介系を食べます。
コロナ禍で外食は減り、家でゆっくり晩酌を楽しむことが多くなりました。
近所には安くておいしい弁当店があり、デパ地下には色とりどりの惣菜がそろっているので、肴には事欠きません。
ワインを飲むようになって非常によいことがひとつありました。
それまで私はつきあいの悪い人間で、あまり友達を作らず、バーでバーボンを一人飲みすることにはまっていました。
ワインを飲みはじめてからは、いろいろな分野の人と知り合いになったり、友達ができたりと楽しみが増えました。
「ワインは人と人をつなぐ」といわれていますが、本当だなと思います。
診断は受けていないのですが、症状からしておそらく私は過敏性腸症候群だと思います。
毎朝激しくおなかを下すため、下痢止めを飲んでいます。
晩酌のワインが下痢の引き金になっている可能性は濃厚ですが、ワインを止めようと思ったことはありません。
人生は選択の連続です。
おなかをとるか、ワインをとるかと言われたら、生活を豊かにしてくれるワインをとります。
たとえ長生きしなくても元気に仕事をこなし、日々楽しく暮らすほうがいいと思っています。
引き算医療とは距離をおき、薬は必要最低限にとどめ、心と体に必要なものを足し算しながら心地よく暮らすことを意識しています。
ただし、これが正解かどうか、今はわかりません。
私は自分を使って人体実験を続行中というわけです。
私が80歳、90歳まで元気でいれば、「和田が言ってることは確かだね」という話になるでしょう。

足し算健康術は高齢者が「幸せ」を感じるための方法
長年、高齢者医療の現場にいて感じるのは、高齢者の意識の変化です。
かつては「長生きすることが幸せ」という人が大多数でしたが、今では「長生きより元気でいたい」に意識がシフトしています。
こうした思いに応え、「高齢者に今よりもっと元気になってもらいたい」と考え、「足し算」健康術を考えだし、ここに発表させていただきました。
これまで6000人以上の患者さんの診療にあたり、多くの学びをいただいた恩返しでもあります。
私たちはよく「いつも元気だね」とか「ずっと元気でいたいな」などと言います。
あらためて「元気とはなんだろう?」と問い直してみると、気持ちが前向きで、よく笑い、よくしゃべり、よく食べる、足腰がしっかりしている、とさまざまな事柄が思い浮かびます。
つまるところ「幸せだなあ」と感じられることが元気の本質ではないかと、私は考えているのです。
「足し算」健康術は、高齢者のみなさんが頭と体をシャキッとさせ、「幸せ」を感じていただくための方法です。
WHOは健康の定義を、「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあること」としています(日本WHO協会訳)。
健康観というのは主観的なものであり、メンタルの側面が非常に大きいといえます。
精神科医としての経験からいえることは、メンタルが元気なほうが健康であるということです。
病気を抱えていても、「自分は元気だ」と思ったら健康なのです。
健康を測る尺度は、検査数値や障害の有無ではなく、幸せと思えるかどうかです。
検査データが全部正常でも、気持ちが暗く沈んだまま過ごすなら、健康とはいえません。
足が不自由になり車椅子に乗っていたとしても、「あちこち出かけられて幸せ」と思える。
寝たきりや認知症になっても、人とおしゃべりを楽しみ、おいしいおやつを食べて幸せを感じながら生きられたら健康といえます。
年をとったら、検査数値を気にして食べたいものを我慢するのではなく、好きなものを食べ、やりたいことをやって、その日を元気に過ごしたらどうでしょうか。
自分の人生ですから、自分で決めていいと思います。
最後の10年、20年は、「人生を楽しませてね」と思っていいのです。
昔、「いいじゃないの幸せならば」という歌がありましたが、晩年をどう生きるかは、まさにそうだと思います。
「足し算」健康術でみなさんの幸せが増え、充実した毎日が送れるよう願っています。

◇◇◇◇◇
なお、本稿は書籍『シャキッと75歳 ヨボヨボ75歳(80歳の壁を超える「足し算」健康術)』(マキノ出版)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
75歳までは知力も体力も余裕があります。元気なうちから体をよく動かし、栄養をしっかりとって、頭を使うように意識することが老化の速度をゆるめることにつながります。70代は老いと闘える最後の世代です。「もう年だから」とあきらめることはありません。元気に老後を送るには、医療とのかかわり方も見直す必要があります。数値が高いからと無理に薬で下げ、活力を低下させる「引き算医療」でヨボヨボになって過ごすなんて嫌だと思いませんか。70歳以降は引き算ではなく「足し算」で心と体を調えていきましょう。本書は、栄養や運動、性ホルモン、サプリメントなど、体に必要なものを足し算する「足し算」健康術をご紹介しています。いろいろなものを足し算すれば、75歳という節目を楽々乗りきり、シャキッと元気に80歳を迎えることができます。