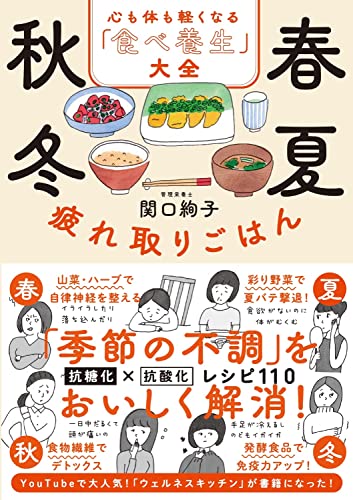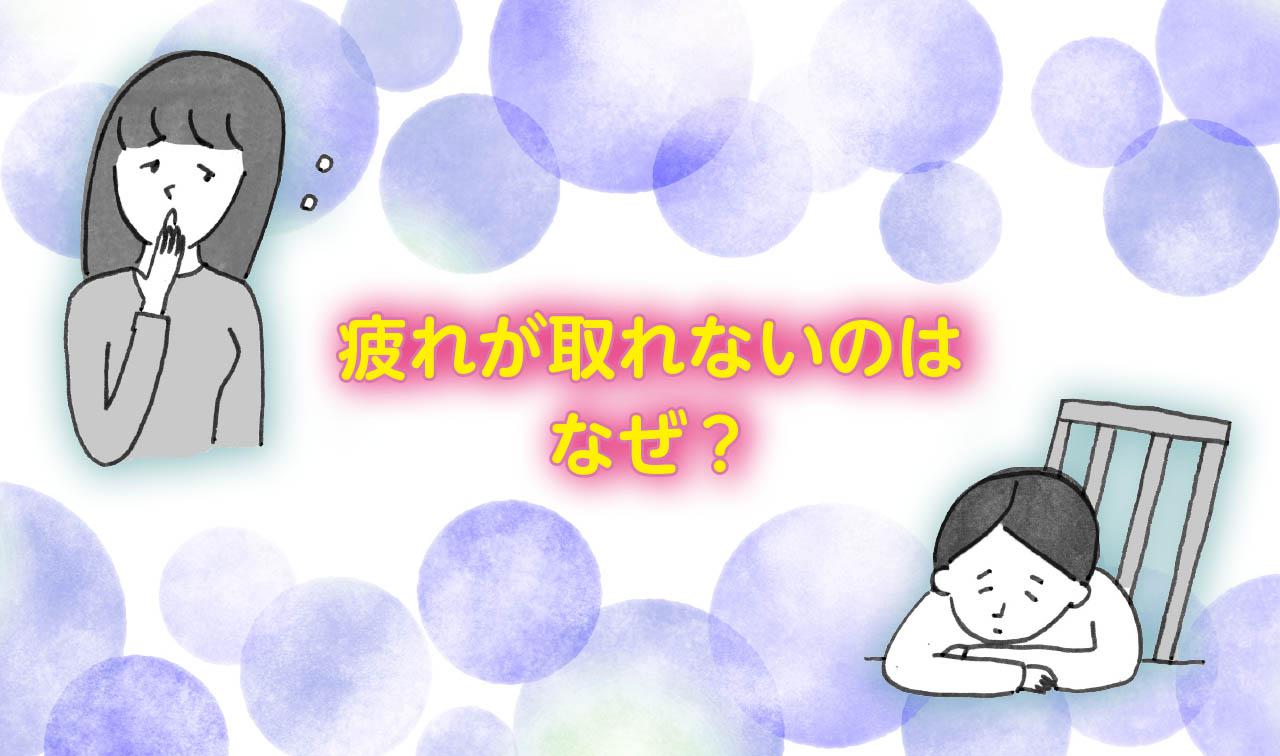私たちの体は、自分が食べたものでできています。体内で起きることに大きく関わる食べものを変えれば、私たちの体が変わるのは当然のことです。いくつもの原因が複雑にからみ合っていることと思いますが、体調不良の原因のもとを探れば、体の酸化や糖化、慢性炎症にあるかもしれません。この3つは老化の三大原因といわれます。生活習慣や食事の取り方、意識して取りたい食品について、書籍『春夏秋冬 疲れ取りごはん 心も体も軽くなる「食べ養生」大全』著者の関口絢子さんに解説していただきました。
解説者のプロフィール
関口絢子(せきぐち・あやこ)
料理研究家・管理栄養士。東京都生まれ、川村学園短期大学食物学科卒業。「食とアンチエイジング」の関係が注目されていなかった15年以上前から、インナービューティースペシャリストとして情報を発信し、先頭を走り続ける。テレビや雑誌等のメディアを中心に、健康・美容・ダイエットに関するレシピや栄養情報を提供。2020年に開設したYouTube「関口絢子のウェルネスキッチン」は登録者15万人を超える人気チャンネルとなっている。米国栄養カウンセラー、ヘルスケアプランナー、日本抗加齢医学会認定抗加齢指導士。
本稿は『春夏秋冬 疲れ取りごはん 心も体も軽くなる「食べ養生」大全』(KADOKAWA)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
イラスト/祖父江ヒロコ
季節の変わり目の不調
やる気が出ない、重だるいなどの疲れに悩んでいませんか? 特に、季節の変わり目は、心や体に不調が起こりやすい時期です。
気温、日照時間、気圧、湿度の変化に加え、生活リズムや環境の変化が重なるので、隠れストレスやダメージを抱えやすくなります。
そんな「季節疲れ」の種類は大きく3つあり、ひとつ目は肉体的な疲労、2つ目は心労、3つ目は季節の変わり目など環境によるストレスです。
3つ目の疲れはあまり自覚されないため、「なんとなく不調」と呼ばれることも。
そうした「疲れ」と「なんとなく不調」を解決するのが、季節の食材や料理です。
旬の食べものには、その時期に必要とする栄養素が豊富に含まれています。
つまり、それぞれの季節で抱えがちな不調を解消するためのパワーが、最もみなぎっているのです。それらを活用して心と体を活性化するということは、自然の恵みから生きる力をいただくということなのです。
体がだるい、心が重い、なんとなく疲れが取れないのはなぜ?
毎日快調で心も体もスッキリ! そんなふうだったら最高ですね。でも実際は日々、体の調子について、健康について、いろいろなお悩みがあるのでは?
いくつもの原因が複雑にからみ合っていることと思いますが、体調不良の原因のもとを探れば、体の酸化(さび)や糖化(焦げ)、慢性炎症(ぼや)にあるかもしれません。この3つは老化の三大原因といわれます。
私たちの体は一般的に、20歳前後をピークとして老化に向かう、つまり衰える方向に向かっていきます。そのスピードは人それぞれですが、避けることは誰にもできません。
健やかな生活のポイントは、老化していく体とうまく付き合うこと。
けれど、ついつい体に余計なダメージを与えて酸化や糖化を進めてしまう。さらには体内に炎症を起こしてしまう。
すると体は疲れやだるさ、痛みといった不調でSOSを出すようになります。
生きていくのに大切な呼吸やエネルギー産生の際に、活性酸素の発生を伴います。
活性酸素は過剰になると、酸化(さび)を引き起こし、疲労や不調の原因となります。
糖化(焦げ)は、体内に取り入れられた余分な糖分がタンパク質と結び付くことで起こります。
糖分につかまったタンパク質は正常に働けなくなり、AGEs(最終糖化産物)を生成します。このAGEsが、老化を促進するのです。
炎症は、本来は体を守るための防御反応ですが、慢性的に炎症が続く状態(ぼや)になると細胞の老化が進み、さらに炎症が加速するという悪循環に陥ります。

酸化しやすい生活習慣をチェック
▼緑黄色野菜をあまり取らない
▼果物をあまり取らない
▼ファストフードやコンビニ弁当、総菜をよく食べる
▼菓子やスナック類をよく食べる
▼加工肉をよく食べる
▼揚げものが好き
▼食事の品数が少ない
▼アルコールをよく飲む
▼ストレスが多い
酸化とは、活性酸素が過剰になった状態。紫外線やストレス、体内の抗酸化作用が弱まることで過剰になり、「疲れ」の原因になります。
体が「疲れ」というサインを出したら
体のさび、焦げ、ぼやは、いずれも生活習慣病や糖尿病、認知症などの原因ともなりえる大きなリスクですが、通常であればいきなり病気になるわけではありません。
体が少しずつ疲れていき、改善しないままダメージがたまっていくことで、ついには深刻な症状が引き起こされるのです。
だからこそ、体が「疲れ」というサインを出したら、酸化や糖化、慢性炎症を抑える行動をはじめないといけません。
私たちの体は、自分が食べたものでできています。体内で起きることに大きく関わる食べものを変えれば、私たちの体が変わるのは当然のことです。
酸化、糖化、炎症を抑えることを意識した質のよい食事を取っていれば、体調は自然と良化していくはずです。
環境やストレスによって受けるダメージにしても、食べもので抑制したり、解消できたりする部分があります。
質のよい食事
「質のよい食事」に絶対コレという答えはありませんが、わかっていることはあります。
たとえばできるだけ、その食べもの本来の姿でいただいたほうがいいということ。
多くの野菜の皮や種には栄養素がぎゅっと詰まっています。捨てずに食べると体にいいものがたくさんあります。
精製したもの(白米、白い砂糖)よりも未精製のもの(玄米、黒糖、きび糖、全粒粉など)のほうがいいのもこのためです。
それは同時に、化学的な調味料や保存料などが少ないほうが安心できるということです。
調味料や加工食品を選ぶときは、ラベルで原材料を確認してみましょう。合成された物質名が多いほど自然から離れていきます。
そうやって、自分が食べているものの内容を知ることがとても大切です。
「今、食べるものが自分の心と体を作るのだ」ということを意識してください。
おいしく楽しく食べられる範囲で、気を付けたいこと、意識したいことを取り入れていけるといいですね。

糖化しやすい生活習慣をチェック
▼朝食をあまり取らない
▼揚げものをよく食べる
▼アルコール類をよく飲む
▼野菜をあまり取らない
▼パンや麺類をよく食べる
▼丼物、カレーライス、パスタなどの単品料理をよく食べる
▼甘い菓子をよく食べる
▼甘いものをよく飲む(コーヒーに砂糖など)
▼あまり体を動かさない
糖化とは、糖分によりタンパク質が劣化して最終糖化産物(AGEs)が生み出されること。AGEsは血糖値の急上昇によって生成が促進されます。
本稿は『春夏秋冬 疲れ取りごはん 心も体も軽くなる「食べ養生」大全』(KADOKAWA)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
目指したいのはこんな食生活
何を食べるかと同じくらい大切なのが、どう食べるかです。
大きなポイントは2つ。「いつ食べるか」と、「食べる順番」です。
私たちの口に入った食べものは、消化→吸収→代謝→排出(排泄)の順番で体のなかを通って体外に出ていきます。その過程で使われるエネルギーは大きなものであり、私たちの体は大変な仕事を24時間フル稼働で続けているのです。
人のサーカディアンリズム(体内時計)は8時間ごとに仕事が決まっています。
このリズムに沿って生活することが、「いつ食べるか」のポイントです。
また、血糖値の変化も体に大きな負担をかけます。体内に食べものが入れば血糖値は上がりますが、食べるものによってその度合いは違います。これが「食べる順番」のポイントです。
食事のはじめに野菜などの食物繊維が多い食品を取り、血糖値の上昇を緩やかにすることが健康のために有効なのです。
次の「体内時計に合わせた食事の取り方」と、「人生100年時代に意識して取りたい食品群」を参考に、自分に合った食べ方のルールを探してください。
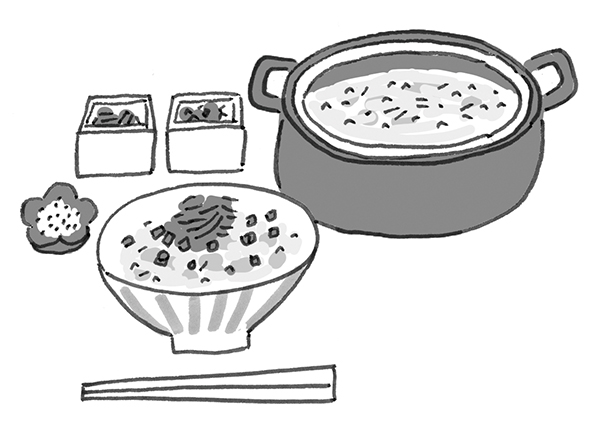
体内時計に合わせた食事の取り方
体のリズムに合わせたエネルギー吸収と代謝を行うことが「疲れ取り」の第一歩。毎日の食事の参考にしてください。
▼4:00〜12:00
体内の老廃物を排出する時間
老廃物を外に出す働きに集中している時間。睡眠中に代謝された老廃物は速やかに排出させたいもの。
朝食に水分、ビタミン、ミネラル、食物繊維、適度な糖質や脂質を取ることで排出を助けます。
▼12:00〜20:00
食事を摂取して消化する時間
食事を取るための時間帯。体内時計に従えば、20時までに消化を済ませるために17時くらいに夕食を食べることが理想です。
食事は20時までに済ませましょう。
▼20:00〜翌4:00
栄養素の代謝と体を修復・再生する時間
新しい細胞を作り新陳代謝を行う時間。疲労回復、筋肉や組織の合成や修復、ストレスの改善などは睡眠中に行われます。
このとき胃腸が消化吸収に忙しいと、ホルモンの分泌が妨げられてしまいます。
人生100年時代に意識して取りたい食品群
抗酸化、抗糖化、抗炎症、血流改善、腸内環境改善、解毒力、脳の活性化などに効果がある、8つの食品群。
各食材から頭文字を取り、キーワードは「健康、主役、決まり」!
▼けん
玄米(げん)・未精製食品
玄米、全粒小麦、雑穀類のほか、豆類、黒砂糖、テンサイ糖、はちみつ、自然塩などの未精製食品。腸内環境の改善、エネルギー産生を担います。
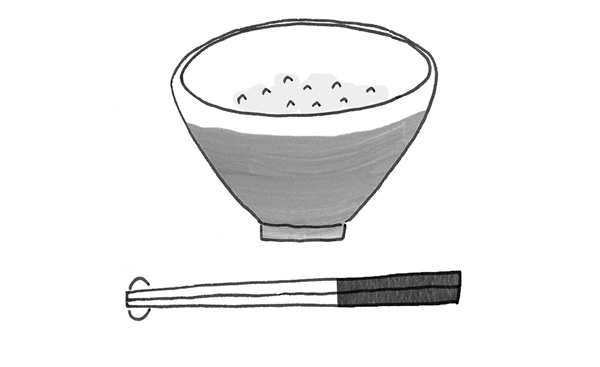
▼こ
根菜
ニンジン、レンコン、ゴボウ、里いも、ジャガイモ、サツマイモなどの根菜類。整腸作用、滋養効果があります。

▼う
海のもの
カキ、アサリ、エビ、イカ、タコ、ワカメ、昆布、のりなどの海のもの。血液浄化、生理機能の回復、免疫力アップに役立ちます。

▼しゅ
種子油類
アマニ油、エゴマ油、オリーブオイル、米油、くるみ、ゴマ、ナッツ類などの種子油類。血管や脳、心の健康を支えるほか、ホルモンや細胞膜の材料となります。
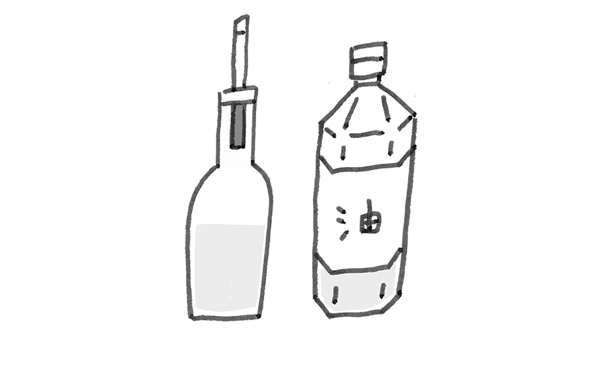
▼やく
生薬(やく)・スパイス
ショウガ、ニンニク、タマネギ、ニラ、大葉、わさび、トウガラシなどの生薬香草類。消化促進、疲労回復、血流改善、代謝促進をサポート。
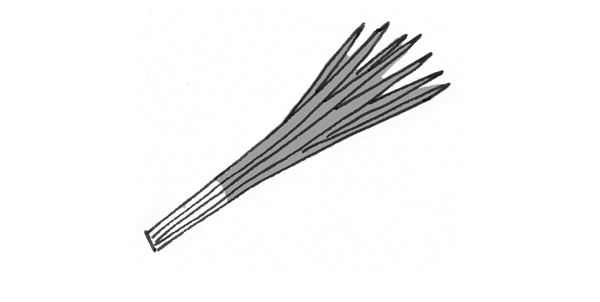
▼き
菌類(発酵食品・きのこ)
納豆、みそ、酒粕、酢、麹、キムチ、ヨーグルト、ぬか漬けなどの菌活食品と、きのこ類。腸内環境の正常化、免疫力アップに役立ちます。

▼ま
豆類・白肉
大豆製品などの豆類と、鶏肉、魚肉(白身、赤身)などのホワイトミート。筋肉や骨の生成、体力を増強します。
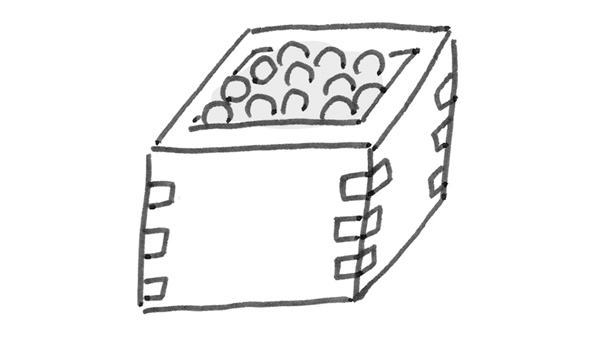
▼り
リンゴ(果物・野菜)
果物と野菜全般。生理機能を高め、抗酸化、抗糖化、抗炎症に効果を発揮。
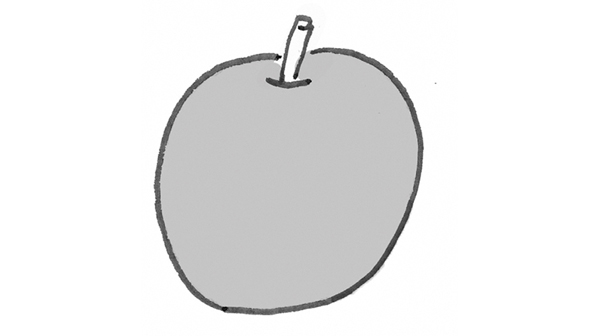
◇◇◇◇◇
なお、本稿は書籍『春夏秋冬 疲れ取りごはん 心も体も軽くなる「食べ養生」大全』(KADOKAWA)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。やる気が出ない、重だるいなどの疲れに悩んでいませんか? 特に、季節の変わり目は、心や体に不調が起こりやすい時期です。「疲れ」や「なんとなく不調」を解決するのが、季節の食材や料理です。本書は、登録者数15万人を超える、著者のYouTubeチャンネル「ウェルネスキッチン」で人気があったレシピを選りすぐり、110品掲載しています。疲れの改善に特に大切な抗酸化・抗糖化を中心に、アンチエイジング、免疫力アップ、デトックスなど気になる情報を1冊に凝縮した集大成となっています。