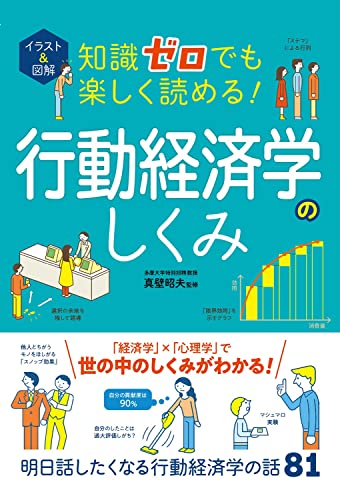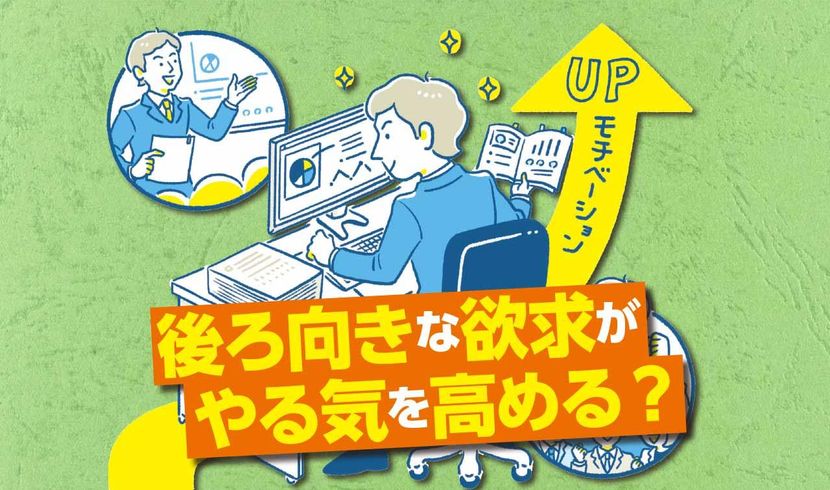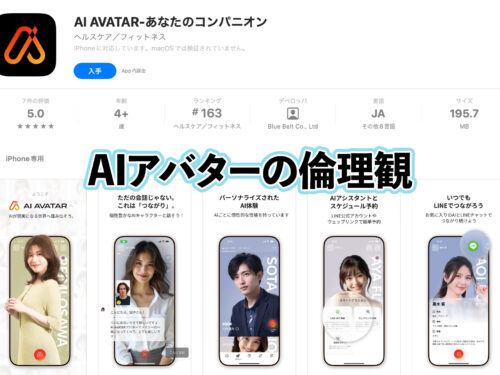「どうしてもやる気が出ない…」。そんな悩みを解消したい人には、行動経済学の考え方を取り入れてみましょう。プロスペクト理論を利用して、モチベーションをアップさせる方法があります。「プロスペクト理論」について、著者で多摩大学特別招聘教授の真壁昭夫さんに解説していただきました。
解説者のプロフィール
真壁昭夫(まかべ・あきお)
多摩大学特別招聘教授。一橋大学商学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行。ロンドン大学経営学部大学院卒業後、メリル・リンチ社ニューヨーク本社出向。みずほ総研主席研究員、信州大学経済学部教授、法政大学大学院政策創造研究科教授などを経て、2022年から現職。「行動経済学会」創設メンバー。『ディープインパクト不況』(講談社+α新書)、『2050年世界経済の未来史: 経済、産業、技術、構造の変化を読む!』(徳間書店)、『MMT(現代貨幣理論)の教科書』(ビジネス教育出版社)、『仮想通貨で銀行が消える日』(祥伝社新書)など著書多数。
本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 行動経済学のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
イラスト/桔川シン、栗生ゑゐこ、フクイサチヨ、北嶋京輔
ヒトの心理を理解して、自分のやる気を上げよう!
「どうしてもやる気が出ない…」。そんな悩みを解消したい人には、行動経済学の考え方を取り入れてみましょう。
行動経済学では、やる気のことを「モチベーション(動機づけ)」といいます。
モチベーションには、報酬や評価などの外的要因による「外発的動機づけ」と、好奇心や探究心などの内的要因による「内発的動機づけ」の2種類があり、効果が長続きするのは、内発的動機づけとされます。
かんたんに言えば、「好き! 楽しい! おもしろい!」と思えることは、やる気がずっと続くのです。

内発的動機づけを高めるには、主体的に行動する「自律性」と、自分が役に立っていると感じる「有能感」、他人と信頼しあえる関係を築く「関係性」という、3つの欲求を満たすことが重要だとされます。
内発的動機づけを高める3つの欲求
▼自律性
自分が主体となって目標達成のために努力したい。
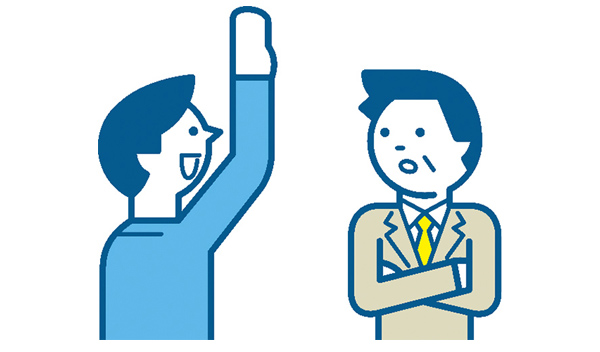
▼有能感
自分が組織の役に立っているという感覚をもちたい。

▼関係性
他人と深く結びつき、信頼しあえる関係を築きたい。
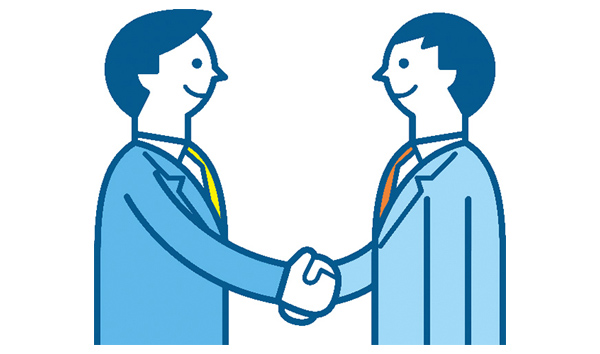
会社なら、自分から積極的に仕事に関わり、成功体験を積み重ね、人間関係を良好に保てると、モチベーションは高まるのです。
でも、そうかんたんではありませんよね?
そこで、「得をした喜びよりも、損をした悲しみの方が大きい」という、「プロスペクト理論」を利用して、モチベーションをアップさせる方法もあります。
つまり、「成功させたい」といった前向きな欲求ではなく、「失敗したくない」といった、後ろ向きの欲求の方が、モチベーションは上がるのです。
成功して喜ぶ自分ではなく、失敗して悲しむ自分の姿をイメージしてみましょう。「やらなければ!」と、焦る気持ちがやる気に結びつくことでしょう。
本稿は『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 行動経済学のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。
ヒトは損を回避しがち?「プロスペクト理論」
ヒトは得した喜びより、損した悲しみが大きい。損得の分岐点が「リファレンス・ポイント」!
ヒトは不確実な状況下で、どのように考え、意思決定をするのでしょうか?
それを理論化した「期待効用理論」では、実際のヒトの行動を十分に説明できませんでした。
そこで、カーネマンとトヴェルスキーは、期待効用理論を修正して、新しい理論を構築しました。
それが、行動経済学の出発点となった「プロスペクト理論」です。
プロスペクトとは「予想」「見通し」を意味します。
プロスペクト理論の要点は、「ヒトの心の中には、得する喜び・損する悲しみの判断を分ける基準点『リファレンス・ポイント(参照点)』がある」というもの。
リファレンス・ポイント(参照点)
プロスペクト理論におけるリファレンス・ポイントとは、利得と損失を分ける基準点。リファレンス・ポイントがちがうと、感じ方も異なる。
▼ボーナスを50万円支給された場合
リファレンス・ポイントが30万円

リファレンス・ポイントが70万円

プロスペクト理論では、ヒトが主観的に感じる喜びや悲しみの大きさを「価値関数」というグラフで示します。
ヒトは何かを選択するとき、「その選択で、どれだけの満足度(価値)を得られるか」を考えます。
価値関数は、「得か?損か?」という、ヒトの主観的な価値を関数で表しているのです。
価値関数のグラフは、リファレンス・ポイントから右が、利益の発生しているプラスの領域で、リファレンス・ポイントから左が、損失の発生しているマイナスの領域です。
そして、左右のグラフの傾きは非対称で、マイナスの領域では、価値が急激に落ちこんでいます。
これは、かんたんにいえば、1万円を得した喜びより、1万円を損した悲しみの方が大きいことを示しています。
ヒトは同じ金額なら、利得より損失の方が、2〜4倍程度、重く受け止めてしまうといわれます。
つまり、ヒトは「損失を避けたい」という意識が強いのです。この性質を、「損失回避傾向」といいます。
また、ヒトは利益が発生しているときは、現状の利益に満足して、「リスク回避的」になりがちです。
逆に、損失が発生しているときは、リスクをとってでも損失を取り戻そうとして、「リスク愛好的」に行動しがちです。
得と損をはさむと、ちょうど鏡に映るように反転になるこの性質は、「鏡映効果」と呼ばれています。
リファレンス・ポイントが「主観的判断」によって移動することも、価値関数の特徴です。
◇◇◇◇◇
なお、本稿は書籍『イラスト&図解 知識ゼロでも楽しく読める! 行動経済学のしくみ』(西東社)の中から一部を編集・再構成して掲載しています。近年、注目されている「行動経済学」は、心理学の理論を応用した、比較的新しい経済学のことです。伝統的な経済学の理論では、人間は常に合理的という条件を前提にしています。しかし、人間は、ときにはおかしなことをする。ダメといわれると余計にやりたくなってしまう。常に合理的とは限らない“私たち”がつくっている社会や経済も、理屈通りではありません。それを考察するのが行動経済学です。行動経済学で使われる言葉には、一般的に理解しにくいものがありますが、具体的なイメージをつくることで理解しやすくなります。それを実現したのが本書です。わかりやすいイラストを見ることによって、行動経済学のおもな理論をより深く理解できるだけでなく、日常の生活にも十分に役立ちます。豊富なイラストとともにオールカラーでやさしく解説しています。