ドイツには「ゲミュートリヒ」という言葉があり、これは「空間が心地いいこと」を指します。家がゲミュートリヒだと言われるのは最高のほめ言葉ですが、私は、清潔で、片づいていて、温かみがあり、リラックスできる空間こそ、ゲミュートリヒだと考えています。【解説】門倉多仁亜(料理研究家)
解説者のプロフィール

門倉多仁亜(かどくら・たにあ)
料理研究家。1966年、神戸生まれ。父の転勤に伴い日本、ドイツ、アメリカで育つ。国際基督教大学を卒業後、証券会社に勤務。結婚後、夫とロンドンへ。その地で料理学校コルドンブルーに通い、グランディプロムを取得。帰国後、料理研究家として活躍。また、ドイツ流ライフスタイルを紹介する本を多数出版。現在は、夫の実家の鹿児島県鹿屋市に家を持ち、東京、鹿児島、ドイツを行き来している。ホームページ:http://tania.jp
空間の心地よさは朝のルーティンで作る
私は日本人の父とドイツ人の母のもとに生まれ、日本、ドイツ、アメリカで暮らしてきました。なかでも母や祖父母の影響を受けて、シンプルで合理的なドイツ式の暮らし方を実践してきました。
ドイツには「ゲミュートリヒ」という言葉があり、これは「空間が心地いいこと」を指します。
家がゲミュートリヒだと言われるのは、最高のほめ言葉ですが、ほこり一つないピカピカなお部屋がゲミュートリヒなのではありません。
私は、清潔で、片づいていて、温かみがあり、リラックスできる空間こそ、ゲミュートリヒだと考えています。
ですから私は、お客様に「居心地がよくて帰りたくないわ」と言われると、とてもうれしい気持ちになります。
ドイツ人がゲミュートリヒをたいせつにするのは、日本人に比べて、家にいる時間が長いという点もあるでしょう。
子どもたちも塾などに行くことは少なく、家にいることが多いため、小さい頃から、徹底したお片づけをしつけられます。「ドイツ人は世界一きれい好き」と言われるのもそのためでしょう。
私がゲミュートリヒのためにたいせつにしているのは、朝のルーティン(習慣)です。
毎朝、9時までに片づけと水回りの簡単な掃除を行うのが私のルーティンで、お客様がいつ来てもいい状態にしておきます。ルーティンにすれば、考える前に体が勝手に動くので楽なのです。
具体的に、私の朝のルーティンをご紹介していきましょう。
だらしない印象をホテルのような状態に

ドイツでは、朝起きたら、まずは窓を開けて換気を行います。すごく寒い日でなければ、30分くらいは開けておき、朝の新鮮な空気をお部屋に取り込むのです。
ただし、ドイツでは「通気は万病の元」と考えられ、風には当たらないようにしています。ドイツの冬は寒く、カゼを引きやすいため、換気中は別の部屋で過ごすのです。
寝室は、起きたままの状態にしておくと、とてもだらしない印象になってしまいます。
私は、幼い頃に、祖父にドイツ式のベッドメイキングを厳しくしつけられ、起床直後に行うことがルーティンになりました。
ベッドメイキングのコツは、シーツを整え、枕や掛け布団に空気を入れて、形を元通りにすることです。
ドイツは日照時間が短く、外に干すという習慣がありません。そのため、枕や掛け布団を軽くたたいて空気を入れ、通気性をよくし、湿気や型崩れを防いでいるのです。
掛け布団は、2つに折り畳んでベッドの端に置いておくと、ホテルのようなきちんとしたベッドが完成します。
朝、このようにベッドメイキングをしておけば、夜、寝室に入ったときに、気持ちいい状態で眠りにつくことができます。
☀︎ここがポイント
「起床直後のベッドメイキングはドイツの祖父に厳しくしつけられました」

シーツの乱れを整える。アイロンをかけたシーツでベッドメイキングをすると、さらに気持ちいい

枕は軽くたたきながら形を整える。こうすると空気が入って、湿気を取り除きやすくなり、清潔感が保てる

掛け布団は寝ているときに下になっていた面が外側になるよう2つ折りにして、ベッドの上に置く
毎日の簡単掃除で年末の大掃除は不要に

浴室や洗面所、トイレなどの水回りは、毎日の簡単な掃除で、水あかやカビを防ぐことができます。
ポイントは、水あかやカビの原因になる水滴をこまめに拭き取ること。これを続けていれば、カビ取り洗剤を使って年末の大掃除をする必要がなくなります。
まず浴室ですが、スクイージーを壁面に掛けておき、シャワーの後はこれでササッと水切りをします。
洗面所は、洗顔をして、髪を整えた後、汚れや水滴をクロスで拭き取ります。床に落ちた髪の毛は、小さなほうきとちりとりで掃除。
トイレは、使った後、洗剤をつけて、ブラシで軽くこすって、2分で掃除は完了させます。
実は我が家では、トイレを使った後、ドアを開けたままにしておくので、いつも驚かれます。閉めていると空気が循環しないからですが、トイレを清潔にしていれば、ドアが開いていても気にならないものです。
いずれも、掃除道具は手の届くところにかけているので、毎日の掃除がしやすく、苦になりません。
かわいいほうきなど、お気に入りの掃除道具があれば、毎日の掃除が楽しくなり、インテリアとしての役割も果たしてくれます。
☀︎ここがポイント
「道具は手が届くところに常駐させます。私は使いたくなる道具にこだわります」

トイレブラシは床に置くと掃除のじゃまになるので、吸盤がついているものを選びタンクの横に収納

お風呂を使った後は、スクイージーで1〜2分水切りするだけで、カビが生えにくくなる

床に落ちた髪の毛は、ほうきでサッと掃く。デザインがすてきなほうきとちりとりは、壁につるしてインテリアっぽく
夜はお片づけをしないでリラックスする時間に

夕食後、洗い物が済んだ後は、お茶を飲みながらおしゃべりをしたり、読書をしたり、くつろぎの時間を過ごします。
このリラックスした状態のまま眠りにつくので、お茶を飲んだコップや、読んだ本は、片づけないままで朝を迎えます。
朝起きて、リビングの飲みっぱなしのグラスをキッチンへ運び、洗って指定席に収納するのも、朝のお片づけのルーティンになっています。
お皿やコップなどはすべて棚にしまい、キッチンには何も出ていない状態にすると、スッキリします。
私は料理教室を主宰していますが、電子レンジも食器洗い乾燥機も持っていません。東京のマンションだと、家電製品の便利さよりも、フリースペースを広くとって、いろいろな用途に使えるようにするほうがいいからです。
炊飯器は、使っていないときはかごに入れて見えないようにしており、温かみのあるキッチンを意識。壁には、雑誌のお気に入りのページの切り抜きやポストカードを貼って、ホッと和めるアート空間を作っています。これらを眺めるのも私のルーティンです。
また、料理教室とは違い、お料理を盛り付ける日常使いのお皿は3枚と決めています。白いものが大、中、深めと3枚あれば、和洋中のたいていのものは盛り付けられます。
お皿を何枚も使わないことも、お片づけを楽にするコツです。
☀︎ここがポイント
「物の数と指定席を決めておけばキッチンに何も出ていない状態にできます」

小さい食器はラウンドテーブルに乗せておけば、回すだけで奥にあるものが取り出しやすくなる

キッチンのカウンターには物を置かないので掃除しやすい。洗い物の後、水滴を拭き取ってカビを防止

これらを眺めるのもルーティン
左:雑誌の切り抜きです。イギリスの有名シェフがイタリアで普通のおばあちゃんに家庭料理のレシピを習うところですが、このおばあちゃんが指折り数えて熱心に話している場面です
右:鹿児島市のライフサポートセンターしょうぶ学園の工房で見つけた絵はがきです
アイデア収納で古い家具をすてきに活用

リビングには、日本のアンティークの和箪笥を3つ置いていますが、実はこの中には食器やテーブルウェアが収納されています。
和箪笥は、母が骨董屋で購入したものだったり、譲っていただいたものだったりしますが、奥行きがあって、使い勝手がいいのです。
食器を収納するのは食器棚、といったぐあいに決める必要はなく、お気に入りの家具を工夫して使うのも楽しいものです。
ワイングラスは、中に仕切りを作ってもらったので、取り出しやすい収納が実現しました。また、収納できる容量のものしか持たないことにしているので、むやみに新しい食器を買わないため、収納家具をこれ以上、増やすことはありません。
料理教室をしているので、たくさんの食器を持っていると思われがちですが、食器はシンプルなものをそろえているだけ。
テーブルクロスやナプキン、季節のお花などで、テーブルに変化をつけています。
このようにリビングは、古いものと新しいもの、日本のものと西洋のものをミックスさせたインテリアですが、とてもなじんでいます。
お客様からは「落ち着けるし、居心地がいい」と好評です。
☀︎ここがポイント
「使うすぐ近くで指定席を決めます。収納できないものは持たない覚悟を」

桐箪笥の中に仕切りを作ってもらって、グラスや湯呑を指定席に収納。取り出しやすく、割れにくい


ダイニングテーブルの隣にある、アンティークの着物箪笥には、テーブルクロスやナプキンが入っている


帳場箪笥にはコーヒーカップやポット、カトラリーを収納。アンティークならではの趣で中の食器が引き立つ

クッションやラグが清潔感をアップする

西洋はイス文化で、リビングのイスやソファにはクッションが置いてあるのが通常です。
このクッションが、リビングの印象を左右するので、夜にくつろいでへこんでしまったクッションをきちんと整えるのも、朝のお片づけのルーティンです。
クッションを軽くたたいて空気を入れると、形が整って、長持ちします。我が家のソファも、東京で20年以上前に買ったものですが、毎日、クッションを整えているので、まったく劣化が感じられません。

クッションは軽くたたいて空気を入れて、へこみをなくして形を整える。リビングがきちんとした印象に


浅く座るのはクッションのためにはNGです
また、フローリングと比べて、カーペットを敷き詰めるとほこりが舞わないので、掃除が楽です。
さらに、リビングでは、カーペットの上にお気に入りのラグをところどころ敷いていますが、これはインテリアのためだけではありません。
人が通りやすいところに敷いておくと、カーペットが汚れにくくなり、週1回、掃除機をかけるだけで清潔さが保てます。
うちのウールのカーペットは、もう20年以上使っていますが、まだまだ使えそうです。
ちなみに、掃除機はドイツのメーカー・ミーレのものを愛用しています。吸引力が強く、カーペットのごみをしっかり取ってくれるところが気に入ってます。
☀︎ここがポイント
「カーペットとじゅうたんの床だから掃除機は週1回でじゅうぶんです」

人が通りやすいところはカーペットの上にラグを敷くと、カーペットが汚れにくくなり、長く使える

心を癒す植物やアートがお片づけのモチベーションに

部屋に植物があると、自然を感じられて癒され、心地よくなります。そのため、我が家もお部屋のあちこちにグリーンやお花を飾っていますが、私は横着な性格なのか、こまめに手入れすることはできません。
そこで、グリーンは週に1度の水やりで育つ、生命力の強いものしか置かないようにしたところ、水やりのプレッシャーがなくなり、気持ちが楽になりました。

窓の外、和箪笥の上……とあちこちに植物が。週1の水やりでOKのグリーンを選べば、枯らす心配がない



また、花を活けている花瓶やオブジェなどは、私がこれまで暮らした場所や旅先で気に入って、吟味して買ったものばかり。
アートも、自分と縁がある人の作品を飾ったり、大好きなイラストレーター・マツモトヨーコさんの絵はがきを額に入れたり、思い入れのあるものだけです。
物をたいせつに長く使うと、さらに愛着が湧きます。そういった物で囲まれた空間は心地よく、お片づけをしてきれいに保とうというモチベーションも高まります。
ほかに、リビングを心地よくするコツとしては、テレビは別の部屋に置き、プラスチックのものは置かないこと。
リビングは温かみがあって、自然が感じられ、歴史や思い出が詰まっている空間にしたいので、無機質なものは置かないことも、ゲミュートリヒのポイントです。
☀︎ここがポイント
「コーナーに鏡があると部屋に光を投げかけます。縁のある人が書いた絵も心を和ませてくれます」

義妹が描いた絵や、旅先で買った家具やオブジェなど、思い入れのあるアートで居心地のいい空間に




合図→ルーティン→報酬の流れを生活の中に

皆さんが、朝のお片づけを生活のなかに根付かせるためには、「合図」→「ルーティン」→「報酬」の流れを作ることをお勧めします。
朝起きて、夜使ったものをあるべき場所へと片づけたら、お部屋は「ゼロ状態」に戻ります。
それから、コーヒーを飲んで朝食を済ませたら、朝のお片づけを始める「合図」。
キッチン、トイレや浴室、洗面所などを掃除して身支度をするまでが朝の「ルーティン」で、安心感とスッキリ感が「報酬」です。
こうして心地いい空間を作って一日がスタートすると、頭も心も整って、本当に自分がたいせつにしたいもの、自分が好きなものは何なのかもわかりやすくなると思います。
古くなったり、壊れてしまったりしたものは捨てるという考えもありますが、修繕できるものは修繕して長く使うというのも味わい深いものです。
カップやグラスが割れても、今は金継ぎできれいに修復でき、そこに絵を付け足すなどの遊び心ある修復も楽しいでしょう。
☀︎ここがポイント
「修繕できるものは修繕して長く使うほど愛着が湧きます」

お気に入りのカップやグラスは、欠けたり割れたりしても、金継ぎなどで修復して、長く使っている


1歳の誕生日から50年以上いっしょのバビちゃんも、ぬいぐるみ修繕のプロにきれいにしてもらった
私の1歳の誕生日にもらった猿のぬいぐるみ「バビちゃん」も、修繕しながらたいせつにしてきた、かけがえのない存在です。ずっとそばで私の人生を見てきてくれました。
バビちゃん、心地いい?
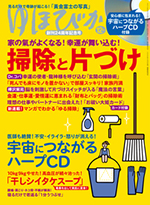
この記事は『ゆほびか』2019年12月号に掲載されています。

